 その「末森城」祉に 城山八幡宮がある。
その「末森城」祉に 城山八幡宮がある。 もともと この地一帯の氏神様で もう少し東の位置にあったのを1936年 今の場所に移した。
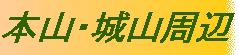
名古屋地方気象台 末森城址・城山八幡宮 大龍寺・五百羅漢 相応寺 桃巌寺

 東山通りから北に入った、小高い丘の上の住宅街の中……街中の気温と気象台発表の気温は違うんじゃないかなと思われるようなさわやかなところ……にあります。
東山通りから北に入った、小高い丘の上の住宅街の中……街中の気温と気象台発表の気温は違うんじゃないかなと思われるようなさわやかなところ……にあります。
所在地は「千種区日和町」、この町名と気象台は関係があるのだろうか?
 1548年、織田信秀がここに城を作り、古渡城から移ってきた。
1548年、織田信秀がここに城を作り、古渡城から移ってきた。
この時、信秀は那古野城を長男の信長に譲り、(信長の)弟の信行を末森城に連れていった。
言ってみれば、新本社を建てて そこに移転する際に 長男を支店に追い出して、弟を新本社に連れて行ったようなわけだ。
母は粗暴な信長を嫌い、信行を可愛がっていたので その影響も大きかったのだろう。
ところが、信秀は末森に移って翌年に死んでしまった。
その葬儀が 万松寺で行われた時、信長は 袴もはかない異様な服装でやってきて、焼香の時も香をワシづかみにして仏前に投げつけたというのは 有名な話である。
信秀が死んだ後、母と信行が末森城に居座り、信長は本家の末森城に入れなかった。
言ってみれば、社長急逝の後 支店長であった長男をそのままにしておいて、たまたま新本社に居た次男を社長後継者にしてしまった ということである。
しかも、本社に居た重役たち…柴田権六勝家、佐久間次右衛門など…も信行側につき、信長は苦境に立つ。
が、やがて信長は 稲生原の合戦(1556年)で信行を破り、翌年 清洲城(その頃信長は清洲城に移っていた)に詫びに赴いた信行を謀殺し 織田家の実権を握る。
この時 末森城も廃城となった。
信長が、桶狭間の戦いで 全国区の舞台に登場するのは その3年後である。
≪城山八幡宮≫
 その「末森城」祉に 城山八幡宮がある。
その「末森城」祉に 城山八幡宮がある。
もともと この地一帯の氏神様で もう少し東の位置にあったのを1936年 今の場所に移した。
標高47m、境内の広さ約1万坪の大部分が末森城祉と重なり、土塁堀など原形をよく保っている。
写真手前の広場が本丸御殿、昭和塾堂のあるところが二の丸だったようだ。
 宇治の黄檗山万福寺の末で、福寿山大龍寺という。
宇治の黄檗山万福寺の末で、福寿山大龍寺という。
享保10年(1725)春日井郡阿原村の地蔵堂を移転し、新出来町に開基。
安永8年(1779)に羅漢堂を落成して、翌年500躯の木像羅漢像をまつったが、もともとは、名古屋城築造の際の犠牲者を供養するために作られたといわれる。
その後、羅漢堂が荒廃したので元治元年(1864)に再建し 羅漢像も修飾されている。
明治15年(1912)に千種区の城山へ移転して現在に至っている。



本堂は寛永10年創建当時のもの。山門額(写真中央)と本堂額は、義直の直筆
元は東区山口町にあったが、昭和のはじめ現在地に移された。
大相撲 名古屋場所の時は九重部屋の宿舎になり 賑わう。
(**今でもそうかな? もし これを目当てに行かれる方は 確認してから行ってください)

 織田信秀の菩提を弔うために、次男 信行が 家老の柴田勝家を督励して作らせた。
織田信秀の菩提を弔うために、次男 信行が 家老の柴田勝家を督励して作らせた。
唐風の門もユニークだが、本堂の隣の「辧財堂」は一度は見る価値アリ。
「眠り辧天」「裸辧天」「歓喜仏」など なかなか面白いものがある。ただし
「眠り辧天」は、いつでも見られるが 全体は お正月の5日間と、5月7、8日の大祭にしか開帳されない。
拝観料 千円はチト高い。
 境内に大仏がある。「名古屋大仏」と記されているが、名古屋に大仏があるのを知っている人は、少ないのではないだろうか?。
境内に大仏がある。「名古屋大仏」と記されているが、名古屋に大仏があるのを知っている人は、少ないのではないだろうか?。

また同じ境内に「角竹」と呼ばれる、四角い竹の薮がある。(写真じゃ、ちょっと判らないかな)。この竹は、秋に竹の子が生えることでもユニーク。