◆--乱を正す 法条を 社会をつなぐ 糧道に--◆
第3.”裁定前支分権成立説” の様々な矛盾
1. 65歳に達した日や障害認定日等の時点では 債権債務関係の成立要件(”決定の裁定” という当事者の意思表示。法16)を欠いており、年金受給権は成立していません。
【当会の見解】
【主旨】
(1)年金基本権は、厚生労働大臣の ”決定の裁定” という ”当事者の意思表示”(下記 ”参考1 → 2 ”)を受給権の法的な成立要件として成立すると定義(法16)されています。
(2)従って、決定の裁定前には、この成立要件に欠けており、年金基本権が成立することはありません。
|
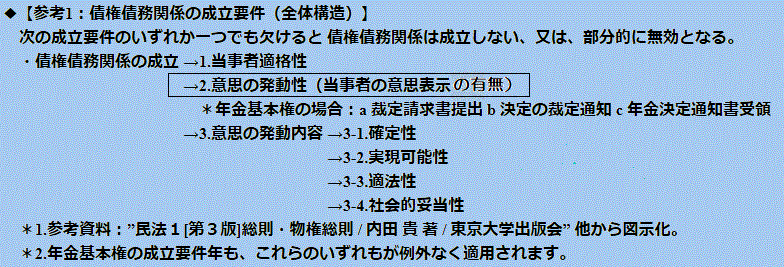 |
【詳細説明】
(1)債権債務関係が成立するには、法的な成立要件として ”当事者の意思表示 ” が必要です。”意思の発動 ” 、” 当事者の合意 ”、”申込 と 応諾 ” とも言われます。応諾債権(⇔法定債権)の成立要件ということもできます。
” 当事者の意思表示 ” を要することについては、民法には明記されていませんが、不文の法・当然の法理とされている定義です(下記 ” 参考 2 ”)。法的と称する所以です。年金受給権の成立であっても、例外となるものではなく、当事者の意思表示を要します。つまり 法16条は、決定の裁定を経て年金債権は成立することを規定するものです。
▼--------------------
【国民年金法】(裁定)
第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
----
◆【参考2:債権債務関係の成立要件 ”当事者間の意思表示(意思の発動)” は不文の法】
山本敬三 / 京都大学教授は、当事者の意思表示という債権債務の成立要件が 現在は不文の法となっていることを、法律行為通則に関する改正の現況と課題 のなかで、次のように明らかにしています(下線部)。
↓↓
(1)法律行為の効力の根拠規定…(PDF2枚目/右列/中段付近)
民法改正の中間試案では(第1「法律行為総則」1「法律行為の意義」(1))、このような規定が必要であるとして、まず、「法律行為は、法令の規定に従い、意思表示に基づいてその効力を生ずる」と定めることが提案されている。…(略)。
このように、法律行為がおこなわれれば、その効力が認められるという原則は、法律行為に関する根本原則であり、民法、ひいては私法全体にとって、もっとも基本的な原則の一つにほかならない。そのような意昧を持つ原則を不文の法にとどめておくべき理由はなく、(以下略)。
---------------------▲
(2)当会の見解と同旨の判例に、NHKの ”受診料基本権”に対する ”受信契約締結承諾等請求事件 ”(H29.12.06最高裁大法廷判決)があります(NHK勝訴。詳しい比較説明は→ ”こちら(準備中) ”)。
ともに、基本権と支分権による債権債務の成立構造をしており、受診料債権は、年金債権と同一の形成過程を経て成立するものです。
年金債権が決定の裁定を経て成立するのに対して、判決では、受診料債権は強制的な契約によって成立するとしています。いずれも、当事者の意思表示を交わして成立するものである点は同じです。
更に判決では、その権利義務構造を次のように厳密に定義し、” 当事者の意思表示 ” を成立要件とすることを判示しています。
【受診料基本権】
…受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が,意思表示の合致の日に成立する旨を述べていると解すべきである(補足意見、18頁18行目途中より)
年金債権では、”意思表示の合致の日” に相当するのが ”決定の裁定の日” に当たり、”受信設備の設置の時” が年金では ”支給すべき事由の生じた日” (例:老齢基礎年金では ” 65歳に達した日 ”、障害基礎年金では ” 障害認定日等の日 ” )に当たります。
この判決による定義を年金債権に当てはめると、次のようになります。
【年金基本権】…支給すべき事由の生じた日からの年金を支払う義務を負うという内容の受給権が,決定の裁定の日に成立する。
(3)裁定前支分権説では、” 厚生労働大臣のする裁定は、単なる意思の確認である ”、” 裁定前の障害認定日等の日に法令に定めた条件を満たしていれば成立する ” などとしています。これを基に、裁定前支分権の前倒しによる成立を展開する主張です。これに対し、前倒しで消滅時効を適用する主張です。
しかしながら、法16条は、厚生労働大臣の ”決定の裁定” という ”当事者の意思表示” を受給権の法的な成立要件として成立すると定義するものです(前述 ”【主旨】(1) ”)。この説の主張は、債権の成立要件に適合せず、法16条に反し、違法です。
そして、年金支分権は、成立した年金基本権を基に、その成立後に到来する各偶数月を支払期月として、派生するものです。年金基本権の成立より 前倒しして成立することは ありません。
2. 消滅時効の対象は ”年金基本権”(法102/1本文)と これに基づく ”本来の支分権”(同 括弧書)に限定されています。裁定前の偶数月は 支払期月には当たらず、仮想の支分権。対象にするのは、規定に反し違法です。
【主旨】
(1)消滅時効の対象になる権利は、年金基本権ついては ” 年金給付を受ける権利 ”(法102/1本文)とし、 年金支分権については ” 年金基本権に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利 ”(法102/1括弧書)に限定しています。
(2)その進行の起算点は、”支給事由が生じた日” とされ、この日から ” 五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。” とされています(法102/1)。
(3)裁定前支分権説によると、支分権は、基本権に基づかなくとも成立するとしています。実在しない ” 仮想の支分権 ” と言うべきものです。例えば、” 裁定を受ける前であっても,(中略)支払期が到来した時から進行する ” (2頁8行目~)があげられます。
その消滅時効の起算点とする ” 支給すべき事由の生じた日の直後から、順次 到来する各偶数月を支払期月とするその各初日 ” は、その年金基本権の成立日よりも前の日に各支分権を成立させたものです。
従って、年金基本権に基づき成立した権利(法102/1括弧書 )には当たらず、権利を行使することができる時(民法166/1)にも至らず、法102条1項を適用するのは違法です。
▼---------------------
【国民年金法】(時効)
第102条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに(中略)支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。(以下略)。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3~6(略)
----
【民法】(消滅時効の進行の起算点)
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2(略)
---------------------▲
【詳細説明】
【消滅時効の対象になる権利】
(1)消滅時効の対象になる権利は、” 年金給付を受ける権利 ” とされています(法102/1本文。一時金は年金ではないので除外されますが、当条項括弧書で対象にしています)。
” 給付を受ける権利 ” 即ち、年金受給権(年金基本権)については、”その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。” とされています(法16)。当事者の意思表示を交わし終えて成立した権利(前述 ”1(1)” )であると定義しているのです。
(2)また、支分権については、”当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利 ” (法102/1但書)と定義し、この定義に該当する支分権を消滅時効の対象にしています。基本権に基づくことなく成立する支分権なるものを、対象にはしてはおりません。
【消滅時効の進行の起算点】
(3)年金基本権の消滅時効の進行の起算点(起算日)は、”支給事由が生じた日” とされ、この日から ” 五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。” としています(法102/1本文)。
また、年金支分権については、” 年金基本権に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利 ” (法102/1括弧書)と定義し、基本権と同様に、” その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する " としています。
(4)更に民法では ” 消滅時効は、権利を行使することができる時 ” を起算点とし、この時から ” 進行する。” (民法166/1)としています。進行とは、将来に向かって進むことであり、過去に遡ることではなく、消滅時効が将来に向かって進むべきものであることを示しています。起算点は、過去に遡らせられないのです。
従って、消滅時効を適用することはできません。遡ることができるのは期間制限(除斥期間)ですが、この旨の規定が設けられていません。このため、5年を超える年金の計算期間を5年に制限することはできません。
(5)”権利を行使することができる時”(民法166/1)とは、消滅時効の対象になる権利が既に成立し、しかも、その権利を行使出来る状態に至っていることを指します。例えば、支給の停止中(法18/2)であって、全額につき停止中ならば(法102/2)、それが解除されるまでは、権利を行使出来る状態にあるとはいえません。
(6)裁定前支分権説によると、支分権は、基本権に基づかなくとも成立するとしています。例えば、最高裁第三小法廷H29.10.17判決 ” 裁定を受ける前であっても,(中略)支払期が到来した時から進行する ” (2頁8行目~)があげられます。
その消滅時効の起算点とする ” 支給すべき事由の生じた日の直後から到来する各偶数月を支払期月とするその初日 ” は、その成立日よりも前の日に各支分権を成立させた日です。
従って、年金基本権に基づき成立した権利(法102/1括弧書 )には当たらず、権利を行使することができる時(民法166/1)にも至らず、法102条1項を適用するのは違法です。
3. 裁定前支分権を 正常に展開できません(法18/3)。
年金支分権だけを、決定の裁定より前倒しして成立させようとするからです。
|
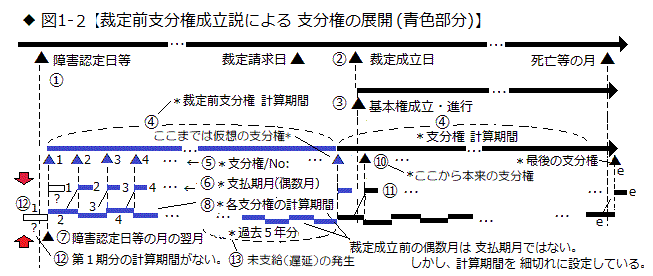 |
(1)裁定前支分権成立説は、裁定前の偶数月が支払期月には当たらないにも係わらず(前記”2”) 細切れに支分権を設定するという 展開誤りを侵しています(上図1-2 ⑤,⑥,⑧/青色部分)。
(2)派生する支分権には分割支給するための年金の計算期間があります。その計算期間は支払期月の ” 前月までの分 ” とされています(法18/3本文)。しかしながら、第1回支分権には計算期間がありません(図1-2 ⑫?印部分)。支分権が派生していないのです。
(3)更に、この説に沿って 第2回以降の裁定前支分権を展開しても、実際の支払の履行(支払期月)は、いずれの裁定前支分権であっても(図1-2 ⑤青色▲1~▲4…)、裁定成立日(図1-2 ②)の直後に到来する偶数月(図1-2 ⑪)とせざるを得ません。複数の裁定前支分権の支払期月が、同一の支払期月(図1-2 ⑪)となるということです。
これでは、細切れに裁定前支分権を派生させたと仮想しても、実際には”図1-2 ⑪”の支払期月により派生する 本来の第1回支分権に含まれていることを示すものです。細切れに支分権が派生したことにはならず、矛盾しています。
▼---------------------
【国民年金法】(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 1~2(略)
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、(以下略)
---------------------▲
4. 裁定前支分権の年金対象期間(法18/1)は、裁定成立後の最初の支分権に含まれるべき期間です(同18/3)。
|
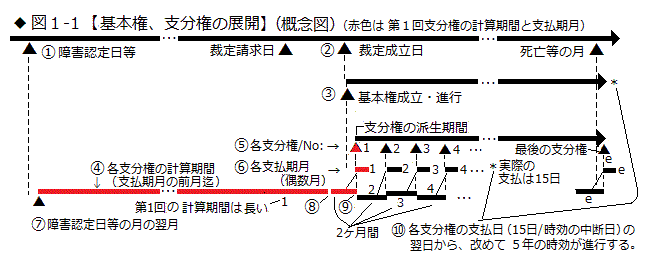 |
(1)最初(第一回)の支分権にかかる年金の計算期間の初年月は、 ” 支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月 ” (法18/1。図1-1⑦)からとされています。老齢基礎年金では ” 65歳に達した日(法25)の翌月 ” であり、傷害基礎年金なら ” 傷害認定日(法30等)の翌月 ” がこれにあたります。
(2)また、最初(第一回)の支分権にかかる年金の支払期月は、年金基本権の成立した日の直後に到来する偶数月(図1-1⑥の1)となります。
(3)そして、年金給付は、支払期月の前月(法18/3本文。図1-1⑨)までとされています。
(4)よって、最初(第一回)の支分権にかかる年金の計算期間は、 ”支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月 ”(法18/1。図1-1⑦)から、”年金基本権の成立した日の直後に到来する偶数月の前月まで”(法18/3本文。図1-1⑨)となります。
(5)従って、裁定前支分権の年金対象期間(法18/1。図1-1⑦~図1-1⑧までの赤線の期間)は、裁定成立後の最初の支分権の計算期間(図1-1⑦~図1-1⑨)に含まれることとなります。
裁定前支分権成立説のように、年金基本権が成立する前の期間を細切れにして、消滅時効を適用するように定義されておりません。
▼---------------------
【国民年金法】(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2(支給の停止・略)
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、(以下略)
---------------------▲
5. この説は、決定の裁定が下されるまでの間は年金の支給も停止させる説でもあります(法18/2)。
すると、時効の進行も停止する(法102/2)法律上の障害が存在し、消滅時効は完成できません。
(1)”年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給を停止する。”(法18/2・要旨)とされています。
(2)そして、” 全額の支給を停止されている間は、進行しない。” (法102/2)ともされています。
(3)裁定前支分権成立説によると、裁定前であっても支分権は成立しているとしています。例えば、” 裁定を受ける前であっても,(中略)支払期が到来した時から進行する ” (2頁8行目~)があげられます。
そして、決定の裁定を待ってこれらの各支分権を一挙に消滅時効させると主張しています。つまり、決定の裁定が下されるまでは、支分権が成立しているけれど、その支給を停止しているとの主張でもあります。
(4)すると、決定の裁定が下されても、それまでの間、時効も停止 (法102/2)していたので、消滅時効を完成させることは出来ません。裁定前支分権成立説は、明文規定(法102/2)を無視し、自己矛盾を明白にした、違法な主張です。
▼---------------------
【国民年金法】(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 1(略)
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3(略)
----
【国民年金法】(時効)
第102条 1(略)
2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3~6(略)
---------------------▲
6. この説は、5年を経過した分だけでなく、5年以内の裁定前支分権にも支払遅延損害金(民法412、同415、同404)の支払義務が生じるという説でもあります。違法な主張を根拠に、損害金を支払うことはしていないハズです。
(1)裁定前支分権成立説は、裁定前であっても支分権(前記 ”5(3)”)、つまり、仮想の支分権が成立し、その裁定前支分権に対して、消滅時効が適用されるという主張です。
(2)支分権が成立するということは、その支払期月の翌月の初日から、履行遅滞に陥っているという主張に展開するものです。履行遅滞に陥っていることを承知しながら、支払を停止させるというもので、法的な根拠のない事実上の停止です。
この状態は、5年以前の仮想の支分権に限らず、5年以内の仮想の支分権、更には、裁定請求をして後、決定の裁定か成立し 本来の支分権が派生する直前まで、継続することになります。決定の裁定が遅れるほど 多くの裁定前支分権が、雨後の竹の子のように成立するということです。
(3)すると、” 債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う ” (民法412/1)こととされ、更に、”債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる ” (民法415)とされています。
この場合、別段の規定がないので、” 年五分” (法404)の損害遅延金を支払う義務が課されます。
▼---------------------
【民法】(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2~3 (略)
----
【民法】(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
----
【民法】(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
---------------------▲
7. あらかじめする 裁定前支分権に対する消滅時効を適用する旨の周知は、 ”時効の利益の放棄”(絶対禁止規定。民法146)に触れ、自ずから無効です。5年を超える年金受給権、同支分権も有効に成立しています。
(1)あらかじめする ”時効の利益の放棄”(絶対禁止規定。民法146)とは、
① 消滅時効の完成する前に、債務者が時効の完成によって享受すべき利益を放棄することをいいます。
絶対禁止規定とは、この放棄の条件を、無条件かつ強制的に無効にするということです。債権債務の全体を無効にするのではありません。
これに反する判決であっても、無効となります。従って、予防的な主張をしないと、これに関する何らの判旨も示されず、5年を経過すると、消滅時効が完成してしまうことになりかねません。
② 放棄は、その旨を相手方への意思表示によっ行われるべきものです。時効の完成後に行われる利益の放棄については、この規定の適用の対象にはなりません。
③ 前記 ”① ” の反対解釈も成り立ちます。即ち、消滅時効の完成する前に、債権者(年金受給権者)が時効の完成によって受忍すべき不利益を、時効の完成前に容認する場合です。通常、年金受給権者がわざわざ容認の意思を示すことはないとみられますので、最初(第1回)支分権の計算期間が5年を超えるのであっても、請求権は維持されていることになります。
(2)一般に向け、又は、裁定請求をしようとする者に対し、ネットサイトや口頭で、裁定前支分権であっても、消滅時効が進行している旨を周知(以下、あらかじめ放棄を周知)する状況が見られます。この旨の書面の提出をあらかじめ求められる場合もあります。
(3)しかし、このあらかじめ放棄を周知の状況下で、決定の裁定に至れば、事前放棄をさせることとなって、無効となる効果が生じます。年金の計算期間が5年を超えた分であっても、自ずから、全額を受給する権利が存在しているということです。
また同様に、裁判官が、あらかじめ放棄を周知の状況下であった時の事件につき、裁定前支分権であっても消滅時効が進行しているとする旨の判決を下しても無効です。法律に明記されている条文(民法146)を、判決によって覆すことはできないからです。裁判官による不法行為(民法709)と捉えられなくもありません。
(4)前述 ”(2)” のあらかじめ提出を求める書面には、例えば、”年金裁定請求の遅延に関する申立書” や ”障害給付裁定請求事由にかかる申立書” があります。
① これらの書面には、 ” 年金の支払を受ける権利について、5年の時効が完成している分については、支給がない旨を理解しています ” などと時効の利益の放棄の確認文、又は、迫られた放棄への容認文が記載されています。これが時効の利益のあらかじめ放棄にあたり、無条件に無効(民法146)となるのです。
提出したからといって、諦めるには及びません。年金の計算期間が5年を超える裁定であっても、全ての計算期間について支給すべきとして有効に成立しているからです。支給の対象にしているか否かは、年金を支給する曲面になって、確認できることとなります。
② しかし、これらの書面は、事前放棄を認容した動かし難い 有力な証拠(直接証拠)として使えるとみられます。求めに応じて提出しておくと、その後に有利な展開が図れます。更に、窓口説明を求めて、その内容を 担当者名、日付とともに記録しておくのも有効です。
間接証拠なら、国民年金法 逐条解説テキスト(市町村 国民年金事務担当者向け。H27.4.1)があげられます。このテキストでは ” 障害認定日等の月の翌月に当然に発生します”としています(61頁<裁定 第16条>中段<参考>より要旨抜粋)。このテキストは、H30.12.05現在 " https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095039.pdf ” として広くインターネット上で周知しているからです。加えて、市町村の年金担当者も、このテキストを参考にして、統一的な窓口説明をしているものと見られるからです。
▼---------------------
【民法】(時効の利益の放棄。絶対的禁止規定)
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
----
【民法】(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
---------------------▲
8. 裁定前支分権成立説の論拠は、判決、解説書によってまちまちです。法的な根拠がないから、その場限りとなり統一できないのです。共通するのは、決定の裁定より前倒しされた ”支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月(法18/1)” に年金支分権が成立しているとの論述です。
|
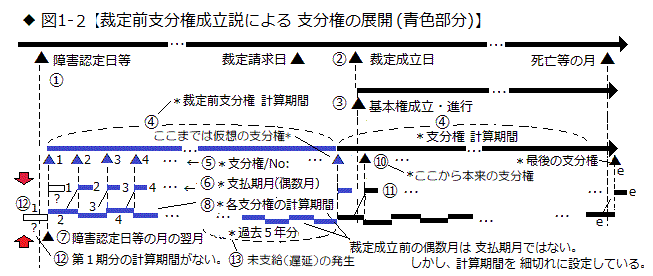 |
(1)裁定前支分権成立説においては、” 決定の裁定前であっても、支分権が成立する ” とする点が共通しています。その法的な成立要件(前述 ”1 参考 1 ”)に関する論拠は見られません。
理由として、次のようにまちまちな理由が並べたてられていますが、共通性がみせれません。( ” 第2.” 裁定前 支分権成立説 ”とは 3” の項より転載)。
① 法令に規定されている要件が揃えば、年金支分権も当然に成立する。
② 裁定請求は いつでもできるから、決定の裁定で認定した障害認定日等の月の翌月(図1-2 ⑦)に既に成立している。
③ 年金支分権は、裁定で認定した障害認定日等の月の翌月に(図1-2 ⑦) 抽象的に成立している。
④ 裁定は、単なる確認行為であって 裁定前支分権の成立の障害にはならない。
⑤ 裁定には裁量権がなく、単なる確認行為である。
(2)これらの主張は、どれ一つとして法律論に根ざした論拠といえるものはありません。
例えば ① では、 ” 要件が揃えば、年金支分権も当然に成立する ” としています。これは、物件の成立要件の定義にあたります。また、法定債権と観念しているともみられますが、年金債権は諾成債権であり、異なります。
更に例えば ③ では、 ” 抽象的に成立している ” としています。抽象的な債権という権利があるとすれば、日本の社会経済構造は破綻してしまいます。都合のいいように権利を主張し 巨万の富を手にしたり、義務を免れる社会となるからです。
これらの理由の是非につきましては、後記 ” 第6.” 裁定前 支分権成立説 ” の総点検 ” の項で述べることにしています。
9. 裁定前支分権成立説は、時効の規定(法102/1)を代用して行う 法的根拠のない 年金支分権の期間制限(除斥期間)であり、違法です。
(1)消滅時効の対象は、成立した債権債務たる ”年金基本権”(法102/1本文)と ”年金基本権に基づき派生する支分権”(同 括弧書き)に限定されています。裁定前の偶数月は 支払期月には当たらず、仮想の支分権であることは、前記”2”で述べたところです。時効の起算点は、過去に遡れないからでもあります。従って、時効の規定(法102/1)を適用して、年金の計算期間を5年に制限することは出来ません。
(2)債権債務が成立していなくても、期間を制限する制度に期間制限(除斥期間)の制度があります(参考法令 / 国税通則法・下記:参考4 ”*1~2 ”)。
期間制限であれば、過去にも遡れるし、特定の期間だけを指定できます。時効制度ではできない 止むを得ない事情を考慮することもできます。
しかしながら、国民年金法では、期間制限の規定を設けていません。
それでも、この説では、消滅時効を適用していると主張するものです。従って、この説は、時効の規定(法102/1)をあたかも合法的に適用するかのように装って、或いは 代用し、期間制限を適用する主張であるいうことになります。時効の規定(法102/1)に反し、著しく違法です。
▼---------------------
【国民年金法】(時効)
第102条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに(中略)支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。(以下略)。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 ~6(略)
----
【参考4】消滅時効の期間と期間制限の違いを、国税通則法では峻別しています。
次の ”*1” は 期間制限の例、”*2” は 消滅時効の例です。
--
*1【国税通則法】第一節(国税の更正、決定等の期間制限)
第70条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(…括弧内略…)を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(…括弧内略…)
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2~4(略)
--
*2 【国税通則法】第二節(国税の徴収権の消滅時効)
第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(…括弧内略…)は、その国税の法定納期限(…括弧内略…)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2~3(略)
---------------------▲
10. 支給の遡及期間を5年に制限するなら、法18条に一項を置くなどの 根拠規定を設ける必要があります。
(1)裁定前支分権成立説では、時効の規定を適用できないにもかかわらず、消滅時効を適用していると主張するものです(前記 ”9 ” )。
(2)しかしながら、国民年金法には、この期間制限の規定がないので、計算期間を5年に制限することはできません。
(3)従って この説は、法第102条1項(時効)の規定をあたかも合法的に適用するかのように装って、或いは 代用して、第1期支分権の計算期間を制限するものです。大胆かつ明確に 時効制度の解釈を歪めた 公序良俗に反する違法な主張であり、適法性(前述”1参考1 3-3”)や、社会的妥当性(前述”1参考1 3-4”)を著しく欠くといわざるを得ません。裁定前支分権は、仮想の支分権であり、成立することはありません。
(4)根拠規定を設けるならば、法18条に項を新設するなどして、第1回支分権の計算期間を5年までとする期間制限をする他はありません。
|
| ☆ ☆
☆ 年金制度は国民の財産!
☆ ☆
☆ |
| |











